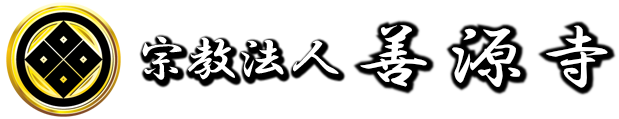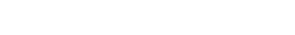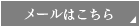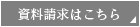価値観の変化 思いの変化
お墓を意識する時

人生には前向きに歩いている時代から、あるとき突然後ろ向きに過ごす瞬間がやってきます。それは人生の残りの時間を計算し始め、その時間内で自分がどのようなことができるのかということを考え始める瞬間です。今までの人生でしてきたことを考え、残りの時間で自分の人生の終焉までの道筋と子孫たちに対して何をしてあげられるのかということを考え始めます。そうした段階で人はお墓や霊園というものについて考えをめぐらし始めるのです。
お墓はその人間が生きてきたひとつの証でもあります。すでにその人間が死んでいる以上その人は現世に対してなんらかの影響を及ぼすことができません。そうしたことから考えるとその人が生きたという証明であるお墓に関してもあまり意味がないものなのかもしれません。では、人々はなぜお墓を作るのでしょうか。
埋葬の持つ意味
原始のころから人間を地中に葬る習慣が人類にはありました。なぜこのようにわざわざ地中に遺体を埋めたのか、そして人類の大部分がこのような埋葬方法をとったのはなぜなのでしょうか。その理由として人間は本能的に腐敗に対する忌避感や嫌悪感があるからでしょう。狩猟などで移動しながら生活をしていた場合、その遺体は置き去りにしてももう二度と見ることはないでしょう。しかし、定住して生活することになると、居住空間に遺体を放置しておくことはできないでしょう。かつて友人や知人、家族だったものが腐敗していくのを見ながら生活できる人はまずいないでしょう。そうした中から、遺体の処理という意味での埋葬が発展したのは生き物として当然のことでしょう。
現在でも人が亡くなれば、埋葬してその遺体を処分します。同様に人が亡くなれば葬儀を行いその人間の死を悼むということも行ないます。しかし葬儀に関しては儀式的な面が多く、行なわなくても生活に支障をきたすことはありません。世界中を見渡してみると、葬儀に関しては方法がさまざまであり、国や地域によっては葬儀らしいものをほとんど行っていないと言える場所もあるでしょう。しかし埋葬に関しては全く何も行なわないという地域はないでしょう。ほとんどの地域が火葬や土葬という形で埋葬を行なっているのです。
遺体の処理という意味ではるかに優れている火葬

火葬と土葬の違いに関しては、まずその機能的な違いがあります。土葬の場合は、地面に穴を掘りそこに遺体を埋めます。あとは地中の分解者などの作用によって遺体が分解されるのを待つのです。場合によっては棺などに入れて地中に葬ることもあります。こうした埋葬方法をとった場合は、外の棺の分解から始まるため完全に分解されるまでに時間が掛かります。利点としては作業としては穴を掘るだけの作業になるため、作業代が比較的に安く済むことがあり、難点としては火葬と比較すると必要な土地が広くなってしまうことや遺体による土壌の汚染、地中で腐敗することによる周辺への公衆衛生の問題があります。
火葬の場合は遺体を高温の火で燃やします。火葬を行ったあとには遺骨や遺灰が残ります。火葬を行う場合、残るものが遺骨と遺灰であるため、土葬のときと比較するとその後の遺体の処分という観点からするとその処分が楽になります。このときに火の温度により残る遺骨や遺灰の量が異なります。温度が高ければその分残る遺骨や遺灰の量は少なくなります。温度が低ければ当然その分その量が多くなります。たとえばインドの場合、火葬から散骨する方法が一般的ですが、その火葬は日本よりも高温で行うため残る遺骨や遺灰が少ないそうです。そういう意味では散骨に適した火葬という方法なのでしょう。利点としては土葬と比較すると遺体そのものの処分が容易になることがあります。費用に関して言うならば、土葬と違い遺体を燃やすという作業が出てくる以上その作業に多くの費用がかかってしまうという難点があります。一方で必要となる土地が少なくなることもあるため土地の価格が高い地域では比較的安く埋葬することができます。また埋葬したあとのことを考えるならば、土壌の汚染がなく周辺の公衆衛生といった面でも土葬よりすぐれた埋葬方法ではあるでしょう。
火葬が世界的に広がりつつある理由 新しい問題点
日本では火葬の割合が99パーセント以上で、土葬を行なっているところはほとんどありません。海外を見てみると、先進国では少しずつ火葬が増えてきています。韓国ではここ30年ほどで急速に火葬化が進んでいます。カナダでも2020年までに火葬の割合が土葬の割合を超えるでしょう。公衆衛生の面や墓地の土地の費用に関しての影響が大きく遺体の処分が迅速に行なえるという点でこれからも世界的に火葬の割合が増えていくと思われます。土葬による土地の汚染問題や衛生面での考え方の変化、また都市部への人口集中による墓地の用地の不足などがあるからです。復活信仰などが信じられていて、エンバーミングなどで遺体を保存している地域を除けばそうした社会的な利点から火葬の割合は増えていくでしょう。
しかし、その一方で火葬を行ったあとの問題も発生しています。それは火葬後の遺骨の問題です。現代の日本でも供養難民という言葉があるように、遺骨の行方に関して困っている人が多くいます。実はこうした状況というのは日本だけではないのです。フランスでも同様に遺骨の行き先で困っている人がいたというニュースがありました。地下鉄の中に遺骨が置き去りにされていたというニュースです。同様の事件が日本でも起きています。駅のコインロッカーやパーキングエリア、電車の網棚に遺骨が置き去りにされているのです。東京駅のコインロッカーに妻の遺骨を置き去りにした男性は、妻の遺骨を同処分していいのか分からずこうしてしまった、と供述していました。2010年のニュースでは両親の遺骨を車の中に置いたまま車ごと放置し、その後死体遺棄として逮捕されました。2008年に両親の遺骨を車に乗せたまま職を失いホームレスとして生活していたからでした。また2007年には神奈川県藤枝市で、神社の境内に白い布に包まれポリ袋に入った状態で遺骨が放置されていました。放置した女性は供養するお金もなくしかたなくそうしたという旨の供述をしていたそうです。このように経済的な理由や遺骨を保持している人の身体的な理由などから遺骨をきちんと供養できないという状況が増えているのです。そのため、処分に困った遺族が遺骨をどこかに放置するという事件が増加しているのです。こうした遺骨に関しては一旦自治体などの公的機関が預かったのち公費で無縁仏として供養しています。埼玉県さいたま市の例を挙げるとするならば2002年には約30件ほどだった無縁遺骨の件数が2015年には約6倍の188件になっており、おそらく今後もその数字は増加していくでしょう。
遺骨という避けられない問題

当然こうした無縁遺骨の数は都市部になれば多くなっていくでしょう。都市部では単身世帯も多く、孤独死などの数も当然多くなります。亡くなった後に親戚などの遺骨の引き取り手が見つかればいいのですが、引き取り手が見つからずそのまま自治体によって処分される遺骨も少なくありません。少子高齢化が進み、子どものいない世帯が増えてくれば今後もこうした事案はどんどん増えていくでしょう。また寿命が延びたことによりそうした状況が発生していることもあります。現在年間で亡くなっている人の4人から5人に一人は90歳以上です。90歳以上の人が亡くなったときにその遺骨の引取りをする子どもの年齢は60歳を過ぎているでしょう。そうした人の中には65歳を過ぎて仕事もリタイアし、自身で行動することがままならず介護などを受けている人も多くいるでしょう。そのような状況で自分の父母の遺骨を管理もしくは処分することは非常に難しいのです。今まで家というもので管理し、そして引き継いでいた遺骨という遺産は現在では処分が困難な負の遺産でもあるのです。
遺骨の処分も含めた供養の方法
逆にこうした状況に対するサービスも現われています。ゼロ葬と呼ばれる、預骨、迎骨、送骨といったサービスがあります。これは遺骨の置き場や処分に困った人たちに対するサービスです。
まず預骨ですが、これは一旦自宅でないところに遺骨を預かるサービスです。現状では供養をすることができないという状況で、ずっと遺骨が自宅のどこかに置いてあるという状況ではその遺族に精神的な重圧がかかることになります。しかし、この預骨というサービスを受けて一旦納骨堂のようなところに遺骨を預かってもらうことによってその重圧から開放されるのです。もちろん最も良い方法は寺院や霊園などにお墓を作りそこに遺骨を供養することでしょう。また永代供養という形で管理を委託してしまうのも良いかもしれません。しかしそこに掛ける費用がない場合やその後改葬を行なう場合など、一時的に遺骨を預かってほしいときにこうしたサービスが利用されています。しかし中には遺骨を預けたまま連絡がとれなくなる人やその預けた本人も死去してしまい、預けられたまま無縁仏になってしまうケースもあるそうです。
迎骨というのは、遺骨を迎えに来てもらうサービスです。自宅にある遺骨を取りに来てもらい、そのままその遺骨をお寺の合同墓などに埋葬してもらうのです。送骨はその逆に遺骨を郵便でお寺に送ります。そうして届けられた遺骨は迎骨の場合と同様にお寺の合同墓に供養されます。どちらの方法の場合も葬式や法要などは行なっていないこと、自身のお墓を所有していないことなどから、葬式ゼロ・お墓ゼロということでゼロ葬と呼ばれているのです。遺骨の最終的な処分ということを考えたときにどうしてよいのかと悩む人は非常に多いでしょう。遺骨をそのまま勝手に放置した場合などは死体遺棄などの罪に問われるからです。また遺骨を地中などに勝手に埋葬した場合にも「墓地、埋葬等に関する法律」に問われる可能性がでてきます。こうした法律や条令の詳細を知っている人は少ないでしょう。そのためどのように遺骨を処分してよいのか分からず困り果ててしまうのです。迎骨や送骨といったサービスの根幹は、寺院などの霊園管理者が合同墓で供養するということにあります。遺骨を持っていくのかどうかという違いはあるかもしれませんが、これは永代供養となんら変わりがないのです。
永代供養の増加 その利点

そもそも永代供養とはなんでしょうか。供養の方法としては大きく分けて二種類あります。それは遺骨の所有権を手放すか手放さないかという違いです。
一般的なお墓を使った供養の方法と言うのは、遺骨の所有権を持ったまま供養をする方法です。地中やお墓に遺骨を埋葬する場合、その土地は都道府県の長が許可を出した場所でなければなりません。一般的には、財団法人や宗教法人が申請を出し許可をもらう、もしくは自治体が自らの自治体の都市計画の一環として霊園を作るということになるでしょう。そのため自身の所有する土地がどれだけあっても墓地や霊園を勝手に作り埋葬することは許されないのです。そのため、寺院墓地や霊園などにお墓を建てる許可をもらい、そこにお墓を建てるのです。この権利の購入のことを永代使用権の購入といいます。寺院や霊園がなくなる、もしくは何か墓地や霊園の存続が不可能にならない限り、そこにお墓を維持し続ける権利を購入するのがこの方法です。一般的にお墓を購入すると言った場合、この方法を指していることがほとんどです。この方法の場合、お墓の中に骨壷に納められた遺骨を納骨します。その遺骨は少しずつ分解や風化をしていきますが、完全になくなるまでには長い年月がかかるため、のちに改葬などを行なうことができるのです。しかしこの方法の場合、墓の管理をする墓守にあたる継承者が必要です。また毎年の管理費が必要になるため、長い間保持した場合に予想外の費用が掛かる可能性があります。
もうひとつの遺骨の権利を手放さずに供養する方法として手元供養と言う方法があります。この方法の場合、自宅など供養している遺骨の管理者がそのまま遺骨の処分をせずに手元に遺骨を保持し続けるのです。しかし、こうした供養の仕方を意図的に行なっている人は非常に少ないです。自宅に保管していてもいずれは処分をしなければならないのが遺骨です。さまざまな事情から一時的に保持することはあっても、最後まで遺骨の保持を考える人は少ないでしょう。
永代供養の利点と問題点
遺骨の所有権を手放す供養の方法にはいろいろあります。しかし、どの方法を選択したとしても、遺骨は最終処分されもう手元に戻ってくることはありません。
一般的に言われるのは先に挙げた永代供養という方法でしょう。言葉を選ばずに表現するのであれば、永代供養というのは遺骨の処分を霊園もしくは墓地の管理者に一任し、完全に手放す方法だからです。遺骨の最終的な処分の方法は地中に埋めるケースがほとんどです。合同墓として地中に埋葬するのか、それとも樹木葬という形で樹木の根元に埋葬するのか、もしくはその他の方法で処分するのかの違いはありますが、最終的に遺骨を処分することに変わりはありません。お墓を引き継がず、遺骨の管理を放棄するというのが永代供養なのです。
最近では多くの供養の方法に永代供養が付帯していることがあります。というのはだれかが亡くなってしまった直後に遺骨を手放すのは忍びないが、将来的なことを考えたときに何十年もお墓を維持していくことが難しいということです。そのため、通常の永代使用権を購入した供養をした場合でも将来の墓じまいについて考えなければならないのです。
墓じまいをしなければならない理由

現在では多くのお墓に墓じまいの必要性があります。熊本県ではおおよそ三割ほどのお墓が無縁仏になっています。それだけのお墓が管理されず放置されれば当然のことながら霊園は荒れ果てていきます。墓所も家と同じです。そこに人が立ち寄ればきちんと管理され荒れ果てることはありません。しかし一旦人がいなくなると自然の力によって人の場所ではなく自然の場所に戻ってしまうのです。全体の三割が全く管理されていない状況になれば自然の力が勝ってくるのは自明の理でしょう。いくつかのお墓が荒れていけばその雰囲気も近づきがたいものになっていき少しずつ放置されるお墓も増えていくことでしょう。もうひとつの直接的な原因として、人口が単純に減少しているということがあります。特に地方都市では過疎化が顕著です。そのため、お墓を管理する人が減りもともとそこにあったお墓を維持するのが難しくなっているのです。そうして荒れ果てていったお墓に対しては自治体が費用を負担して墓じまいを行なうこともあります。しかし人口が減り、歳入が減少している以上、そうした生産性を高めるための事業ではないことに予算を割くことは難しいと言うのが現状でしょう。
減少しつつある伝統的なお墓 変わりつつある死後への考え
以前では考えにくかったことですが、現在では新しくお墓を作る数よりも墓じまいでお墓を撤去する数の多い霊園もあるそうです。この背景には単純な人口の増減以外に現代の人たちのお墓に対する意識の変化もあります。
まずひとつの理由として挙げられるのは、お墓を管理してくれる後継者がいないため、家族墓や個人墓と言った形でお墓を作ることができない人の増加です。2015年の国勢調査データによると男性の生涯未婚率の推計は23.4パーセント、女性の生涯未婚率の推計は14.1パーセントです。結婚していても晩婚化が進む現在では結婚しても子どもがいない状態なのです。こうした流れはどんどんと進んでいます。これから10年も経てば更に生涯未婚率は上昇し、子どものいない世帯は増えていくでしょう。また離婚率もどんどんと上昇しています。離婚すれば子どもが相手方に引きとられる可能性もあります。自身の跡を継いでくれる人がいない、そういう人がこれからどんどん増えていくことになるのです。そうした状態で今までのように個人墓や家族墓を利用して供養を進めていくのは難しくなっていくでしょう。
しかし、自身の供養ということを考えたときに誰かに手を合わせてほしいと考える人は多くいます。そうした思いから生まれたのが、「墓友」という言葉であったり、そうした死後のことを考えて支援していくNPO法人などです。墓友というのは、一緒のお墓に入る友達というものです。
現状入るべきお墓を持たず、かつ身寄りもない。そのうえで特に親しくしている親戚もいないため、死んでしまえば無縁仏になってしまうという状況からこうした運動は起こりました。生前の段階で入るお墓を取り決め、そこに地縁も血縁も異なる人間と入る。その墓にともに入る人間と生前に友人としてお付き合いをすることによって、死後の世界が寂しくないようにするという発想なのです。
またこうした関係性を募集し管理を行なっている団体もあります。そのお墓に生前登録した人間が年に一度集まり、合同法要を行ない先に亡くなった人間を供養します。そしてその登録者がなくなればその合同墓に埋葬されるというサービスです。本来お墓というのは生前になんらかの関係があったもの同士で祀られるものです。例えば家族墓や先祖代々の墓などというものは血縁関係があるもの同士で祀られています。また昔ながらの地域にある寺院墓地などでは同じ地域に住むもの同士が一緒の墓地に祀られています。このようにお墓というのは多くの場合生前のしがらみによって成り立っている部分があるのです。しかし社会の変化や地域との関係性の希薄化などが進み現在の日本では孤独化の進んだ社会となっています。これはある意味では社会と技術が成熟し、コミュニティーを作らなくても生活できるような基盤ができたことの証明なのかもしれません。しかし、その半面で関係性の希薄化は最終的に人間的なところで、言うなれば生物的な面での人間の問題点を浮き彫りにするものなのかもしれません。
人間は社会性を持った動物です。そのため何千年、何万年前から集団を構成して生きてきました。葬儀や供養などは人間独特のものであり人間が生き物である以上、人間は死んだあとに自らの葬儀や供養を行なうことはできないのです。そのため、葬儀や供養というものについては個人の周辺である地域という共同体がルールを決め取り仕切って来ました。しかし人口の流動性が高くなり、その地域の独特の風習が減っていき、日本という国単位での画一化が進んでいくにつれてそうした共同体における葬儀というものは薄れていったのです。現在では葬儀は葬儀業者によって行われるものであり、そこに地域という共同体の差し挟むものはほとんどなくなってきました。
所属する社会的なものの弱体化
人間が死という避けられないものに挑むにあたって、あらためて自分というものを見直したときに、生きてきた足跡として残しているものがほとんどないというのは辛いことだと感じ始めたのではないでしょうか。誰一人帰ってきたことのない死出の旅路に赴くにあたって、現世のように一人で歩んでいくのではなく、ともに歩く誰かを必要としているのではないでしょうか。
日本の従来のお墓は家族というシステムを基盤としたものでした。それは日本の社会が小さな家族という単位から構成されているものだったからです。そのシステムに入れないものは死後にも差別される。それが恐ろしいから自身の家というものに帰依するというのが従来のシステムでした。しかし情報技術の向上や人口の流動性の高まりによって、個人主義が進んでいきました。かつて日本で見られた祖父母、両親、子ども、という三世帯による家族構成はあまり見られなくなってきました。核家族化や単身世帯化が進むにつれて家というものはどんどんと力を失っていきました。家だけでなく所属するものそのものが力を失っていったのです。
その証拠として年功序列、終身雇用であった雇用制度も変化をしています。多くの企業は新入社員を定年まで面倒を見るということはしません。また、入ってきた社員にひとりずつ社員教育を施すということも難しいでしょう。ベンチャー企業を設立して多くの社員が独立する。大きな会社と言えどもいつ潰れたりリストラにあったりするかもわからない社会ではその所属組織に尽くすというのは難しい話でしょう。個人主義や欧米化が進んでいる現在では、すべてのことに関してひとりひとりが責任を持って生きていかなければなりません。しかし、一方でかつての日本にあったような人とのつながりをみなが求めているのも事実なのです。
もうひとつの新しいサービスとしてスマートフォンのアプリを使ったものがあります。これは生前に親族や知人などに向けてメッセージを残しておき、自分の死後に再生してもらうと言うサービスです。またバーチャルお墓という形で、実際にそこにお墓はありませんが、現地に行きスマートフォンアプリを起動させることでそこに家族墓の姿を見ることができるというサービスです。そこまでするのであればなぜ実際のお墓を作らないのでしょうか。実際のお墓を作るということになればそのお墓を片付けることまで考えなければなりません。またそこに物を遺すということは、それは誰かに処分などの義務を残すことになってしまうからです。
生きてきた証 その価値観の変化
自分が死んだあともときどきでいいので自分のことを思い出してほしい。自分が引き継いできた家というものがそこにあったという証明を自分自身で残したい。しかし後世に迷惑になるものは残したくない。そうした思いからこうしたサービスを利用しているのではないでしょうか。
現在多くの人が墓じまいを行なっています。これは後継者や経済的な面から迷惑をかけたくないと考える人が増えたからでしょう。また生前の段階で散骨を望む人が増えています。これは死後に自分の遺骨を遺すことなく自然に還してほしいという気持ちからでしょう。現在の日本の死に対する考えは少しずつ変わっていっています。これは社会の変化からくるものであり、かつての製造と消費を繰り返していた社会が終わり、新しい価値観を受け入れる時代がきたからなのではないでしょうか。
変わっていく形 変わらない形

現代に生きる日本人にお墓の絵を描いて下さいとお願いするとおそらく土台の上に縦長の墓石が乗っていて、○○家の墓と書かれたものを描いてくれるでしょう。これはお墓という固定概念がそうした形でわたしたちの頭に刷り込まれているからです。しかし、同じ質問を江戸時代の日本人にしたらどのような絵が返ってくるでしょうか。鎌倉時代のひとならどのようなお墓を描くでしょうか。
ずっと変わらぬ形で建てられているお墓などありません。それはお墓が時代によって変わっていくものだからです。わたしたちはその途中にある変化の一部を見ているだけにすぎません。これからもお墓と供養の形は変わっていくでしょう。ひょっとしたら数百年後にはお墓というもの自体が物質的に作られることはなくなっているかもしれません。しかし、だからと言ってお墓を作ることが間違っているわけではありません。先祖代々引き継いできた習慣や伝統でもあるため、それを遺し繋いでいくことは今を生きるわたしたちにしかできないことだからです。個人がそれぞれの選択をして、従来のお墓を作ったり引き継いだりしていく。また自分の遺骨を処分することを優先的に考え、永代供養や散骨という選択をとる。遺骨を特殊な技術を使ってアクセサリーなどに変える。バルーン葬などで宇宙に飛ばす。これらの選択はあくまで個人がひとりひとり考えて行なっていくものであり、その結果として残ったものが文化なのです。
光輪霊園は埼玉県東部にある霊園です。宗教法人善源寺によって運営されており、宗教法人善源寺は昭和51年に開山されてから多くの葬儀や供養を行なってきました。その頃から多く変わったものもあり、そして変わらないものもあります。光輪霊園は少しずつ変わっていく供養の方法に対応すべく多くの供養の方法をご提案させていただいております。従来の家族墓や個人墓を使った供養の形。合同碑を用いた永代供養の形。樹木葬形式や納骨堂を使用して墓石を用いずに行なう永代供養の形。また従来の墓石を用いた供養の形をしながらも、その墓石や遺骨の供養を最終的に霊園に委託する永代供養付きの供養の形。これからどのような供養の形が人々に求められるのかはわかりません。しかし故人を偲ぶという気持ちだけはこれからも変わらず人々の中にあるはずです。
わたしたち光輪霊園はそうした人々の思いに応えるべく多くの種類のプランをご提案させていただいております。埼玉県東部地域、松伏町周辺の越谷、春日部、吉川などの地域で霊園をお探しの際は光輪霊園にご連絡ください。